こんにちは!ほび犬です!
前回は麻雀のゲーム性について解説しました。
こちらご覧ください。

今日は入門編全7回のうちの2回目です。
主に今回はゲームの進め方について説明します。
1 麻雀の前提知識・麻雀牌の種類
2 場とは何か ゲームの流れについて
3 上がりとは何か 待ちを覚えよう
4 鳴きについて(ポン・チー・カン)
5 基本的な役について
6 点数計算の仕方
7 アプリでの実践してみよう
場とは何か
ゲームの進め方を説明するにあたって
「場」についての説明をします。
キーワードは東南西北(トンナンシャーペー)
です。
前提として麻雀は基本4人でやるゲーム。
まず一つの正方形の卓があり
それを囲むように4人が座ります。
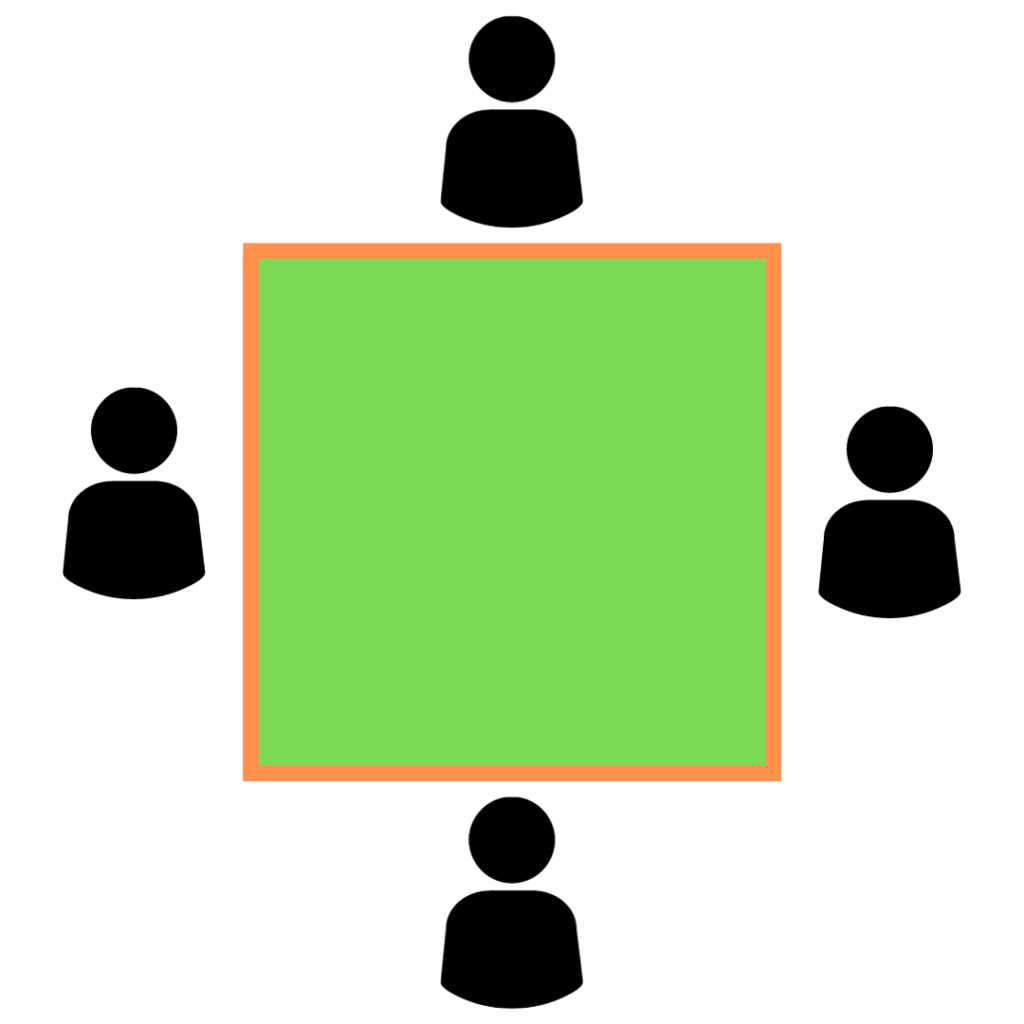
なんとなく想像は付きますよね。
次に2種類の風について説明します。
自風(じかぜ)
それぞれに自分の方角が与えられます。
それが自分の風、自風です。

 ぴよ太
ぴよ太出た!東南西北!
麻雀のメインは東。
全て東からゲームがスタートします。
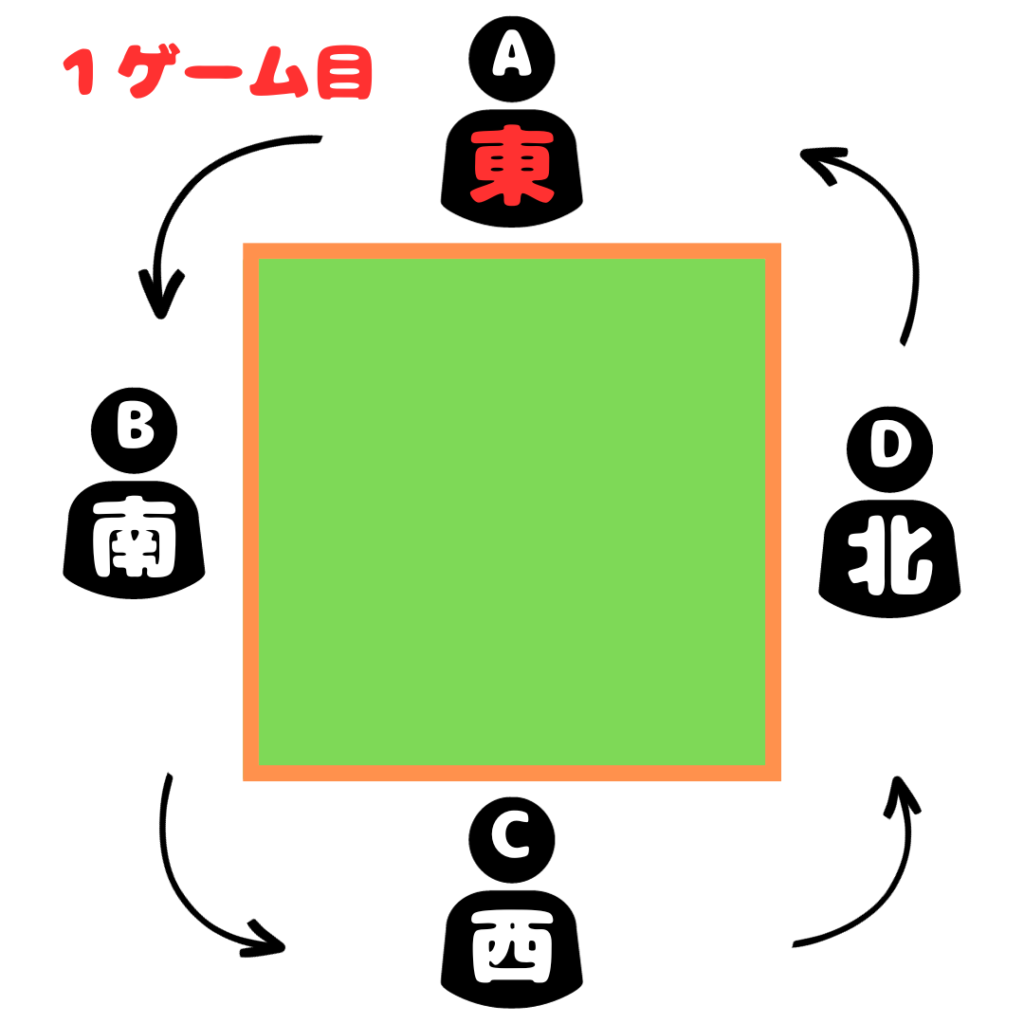
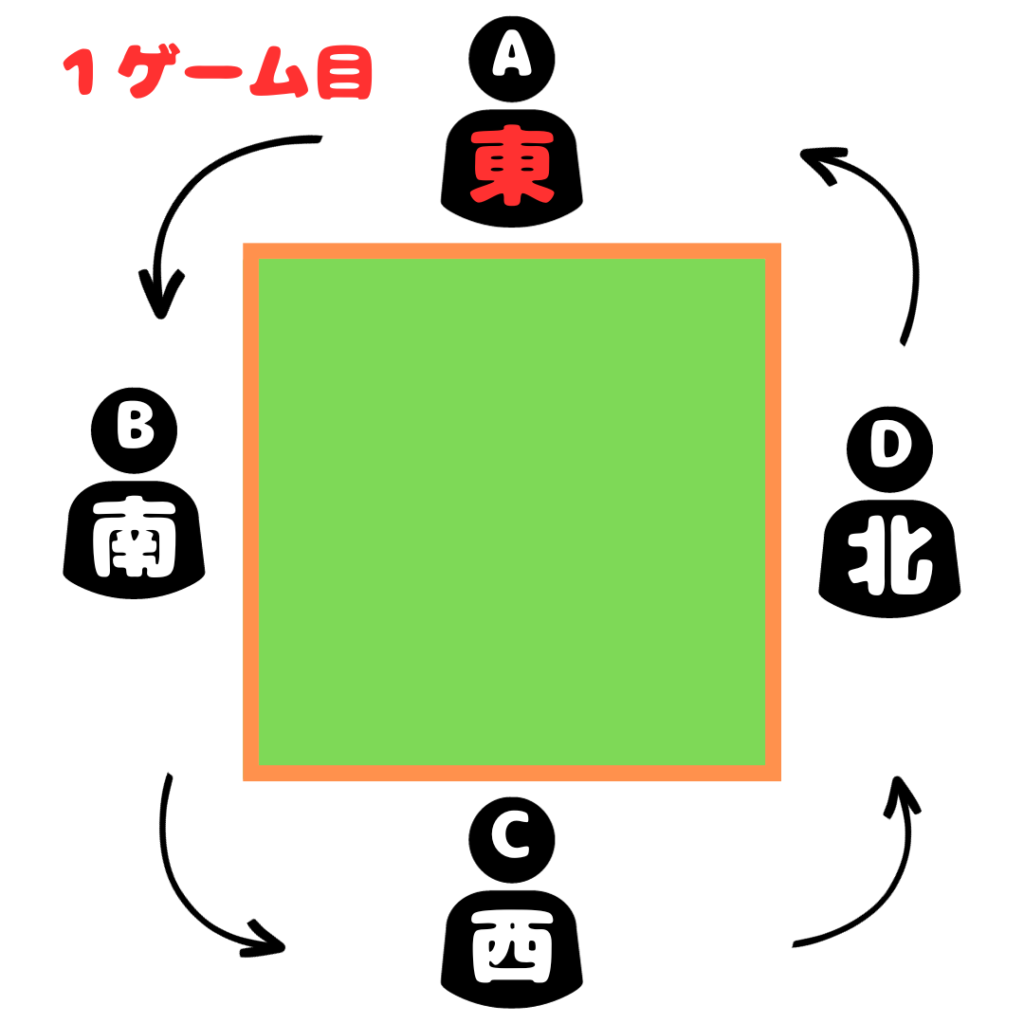
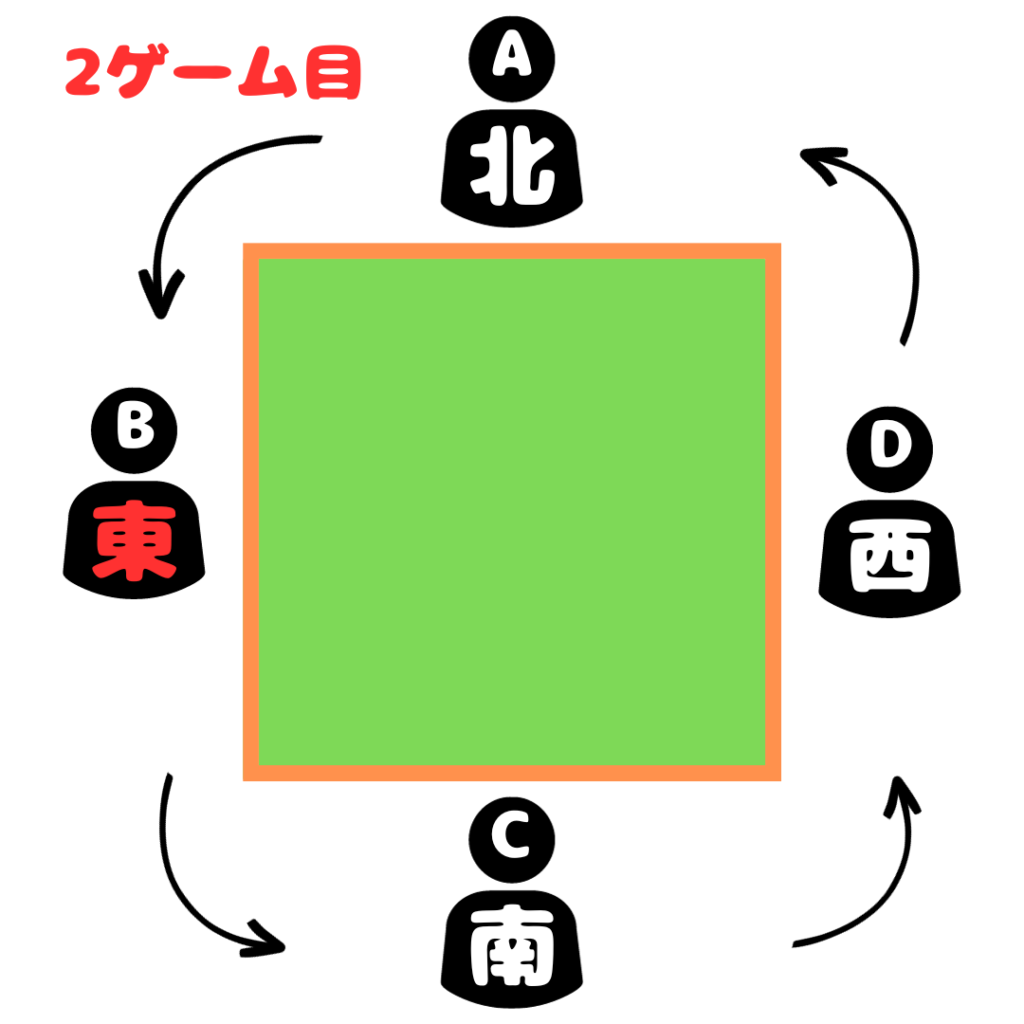
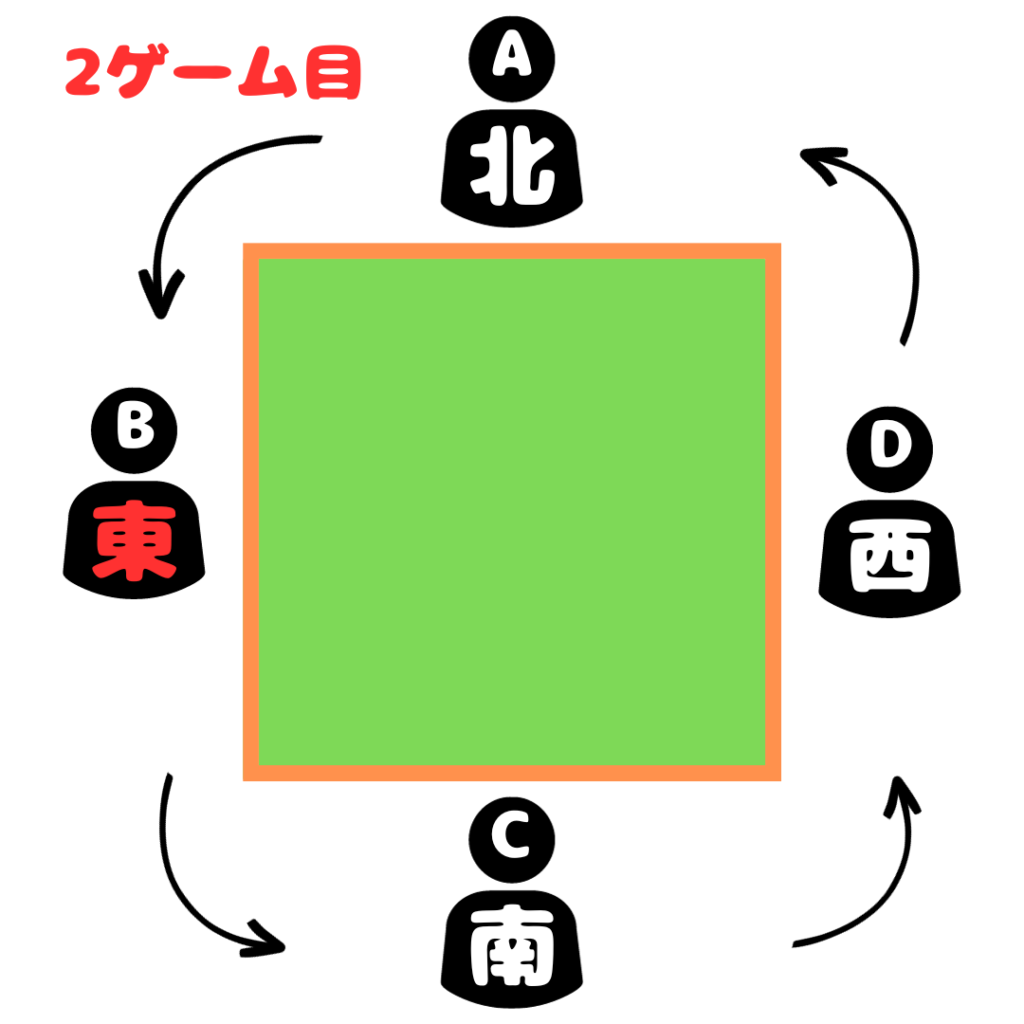
図のように一回ごとに東が右側の人に移動します。
これをくるくる行い、
合計2周して点数を競うゲームです。
1周するゲーム=東風戦(とんぷうせん)
(よりサクッと楽しむ場合)
2周するゲーム=半荘(はんちゃん)
(基本はこっち)
場風(ばかぜ)
場風は場全体に吹いている風のことです。
以下のように場風と自風をの二つがあります。
それぞれ認識する必要があるということだけ
覚えておいてください。




1周目=東場(1-4局)
2週目=南場(5-8局)
※昔は4周やっていたため、一荘(いーちゃん)と呼んでいました。
今は2周だけなので、半荘と呼びます。
家(ちゃ)の使い方
また自風を示す名称として、
「家(ちゃ)」を用いて呼ぶことがあります。
東家(とんちゃ)・南家(なんちゃ)
・西家(しゃーちゃ)・北家(ペーちゃ)
と呼びます。
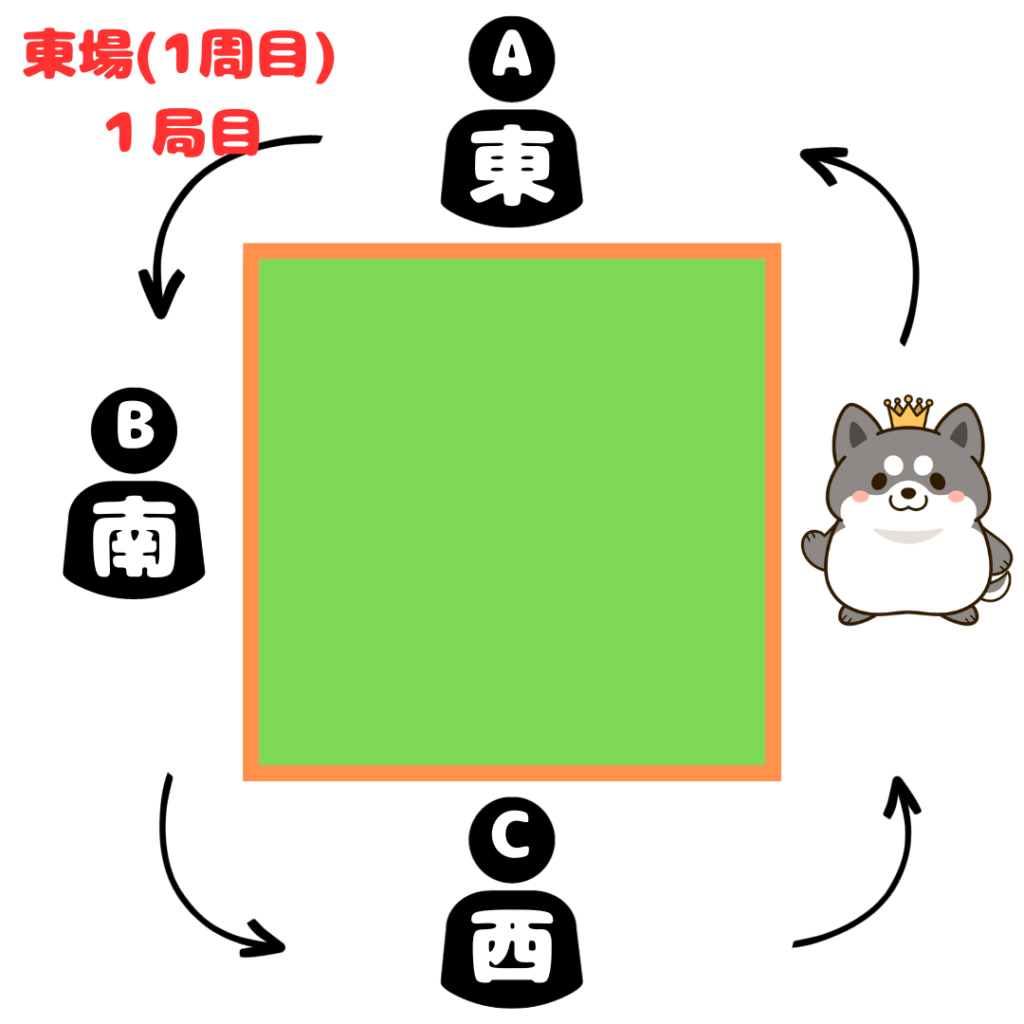
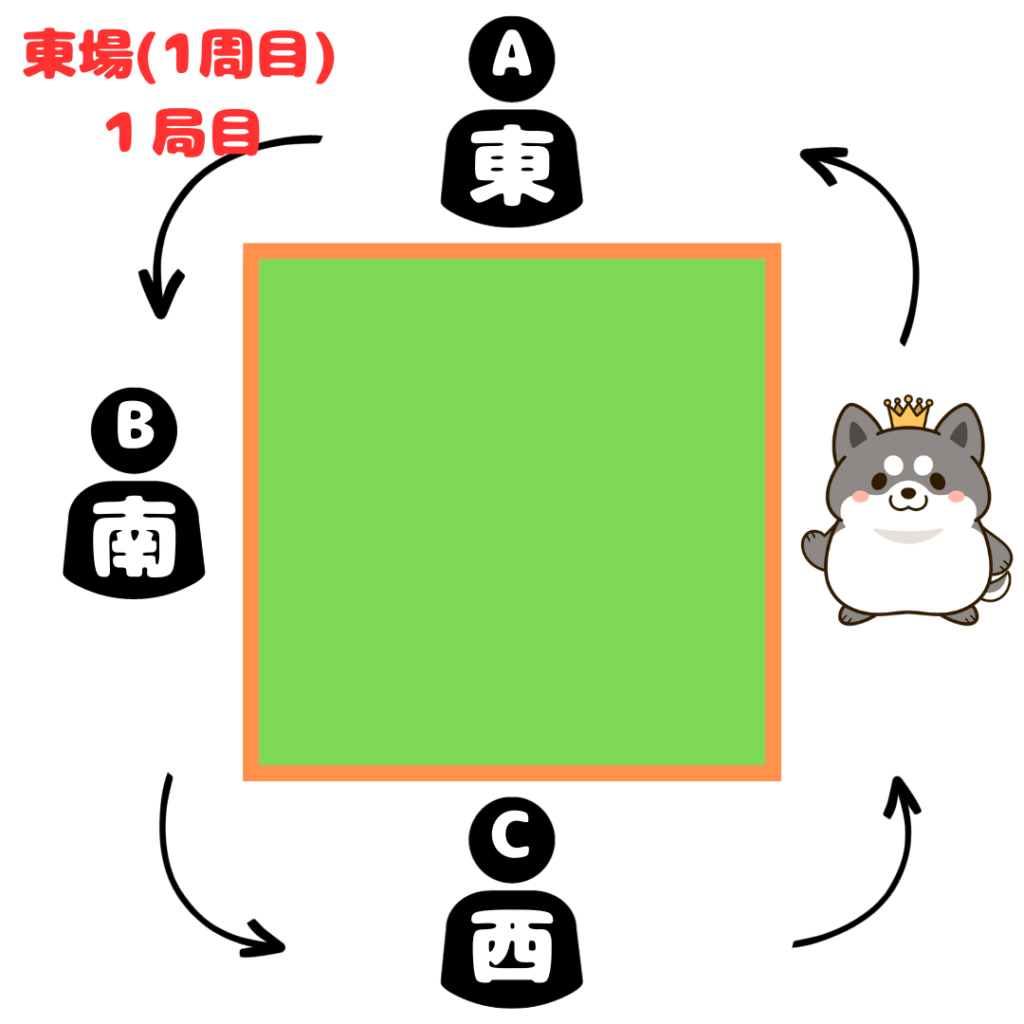
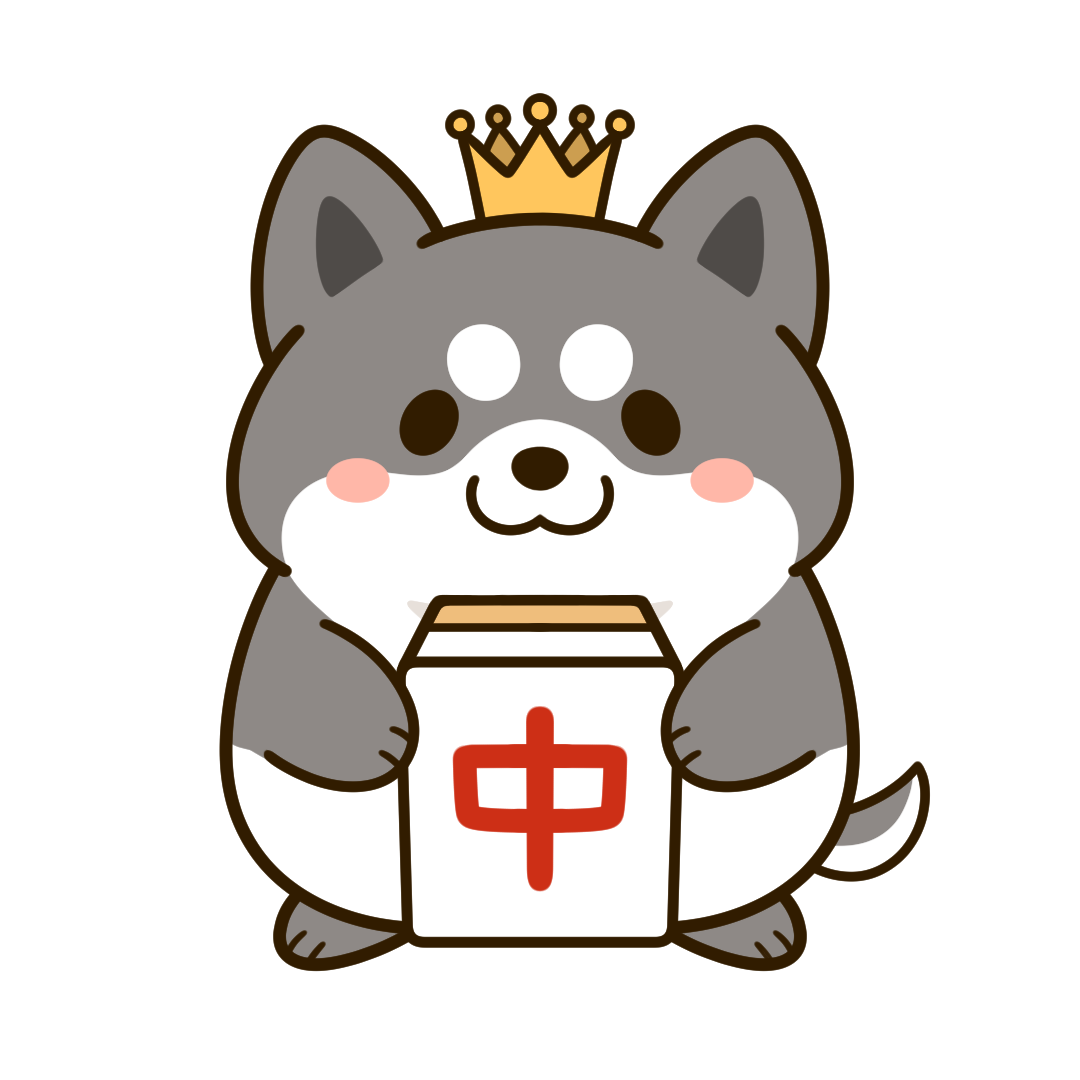
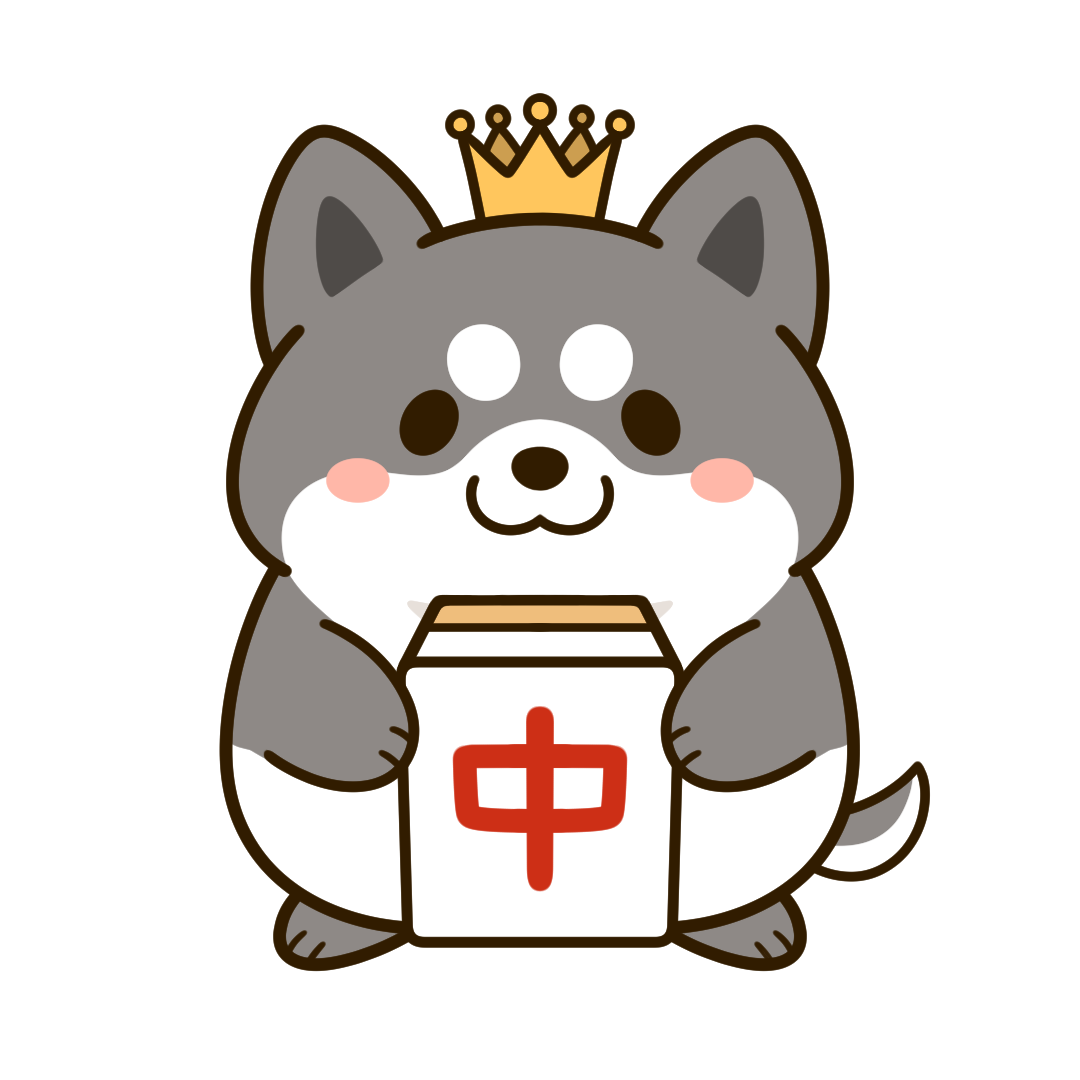
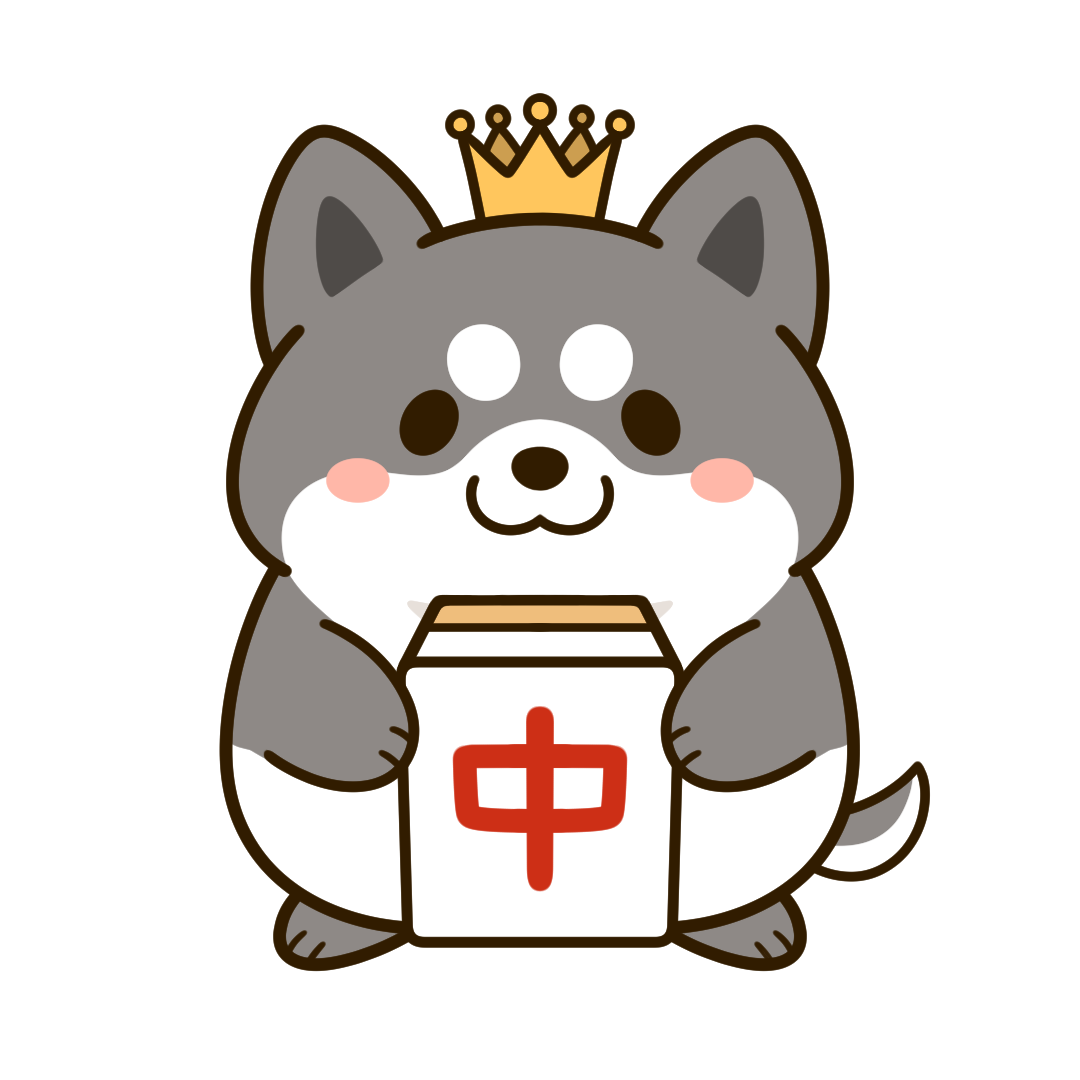
東場の北家だぜ
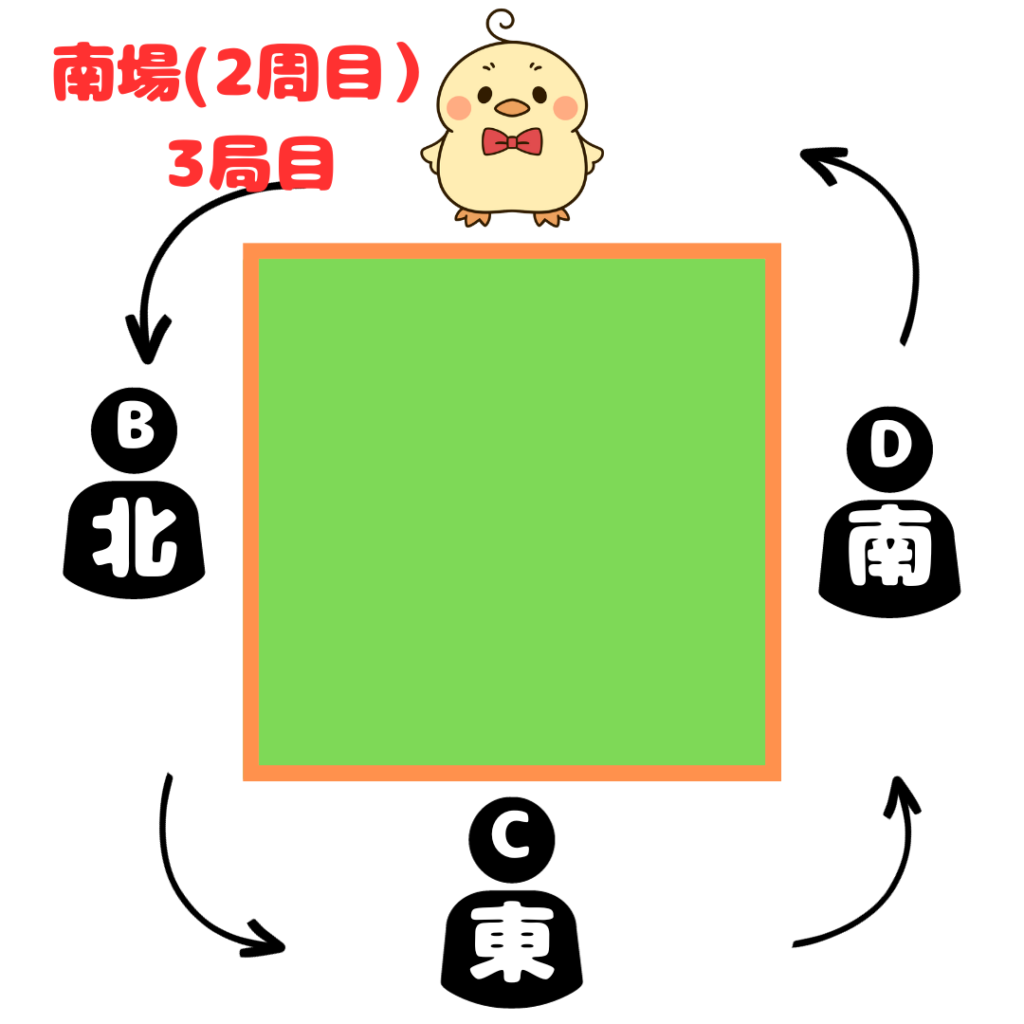
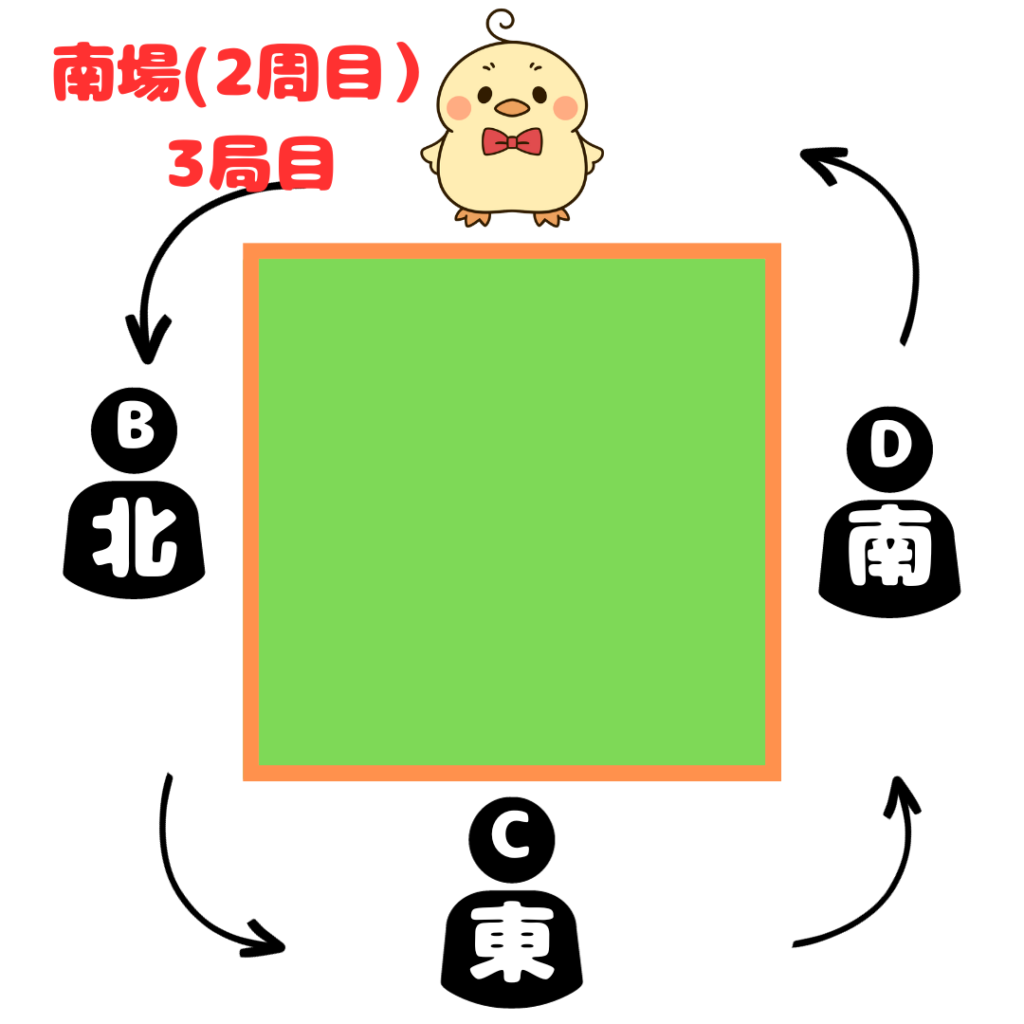



南場の西家だ!
使い方としてはこんな感じです。
後に触れる、「役」とも関わってくるので
方角は大事!とだけ覚えておいてください。
・自風と場風の2種類の風がある
・自風は一局ずつ右の人に動いていく
・場風は自風の1周目を東場、
2種目を南場という
・自風は家(ちゃ)と合わせて呼ぶ
親と子
次に親と子についても触れておきます。
親=東家のこと
子=それ以外の南家西家北家のこと
親=点数が1.5倍になるボーナスチャンスです。
気合いが入ります。図にするとこんな感じ。
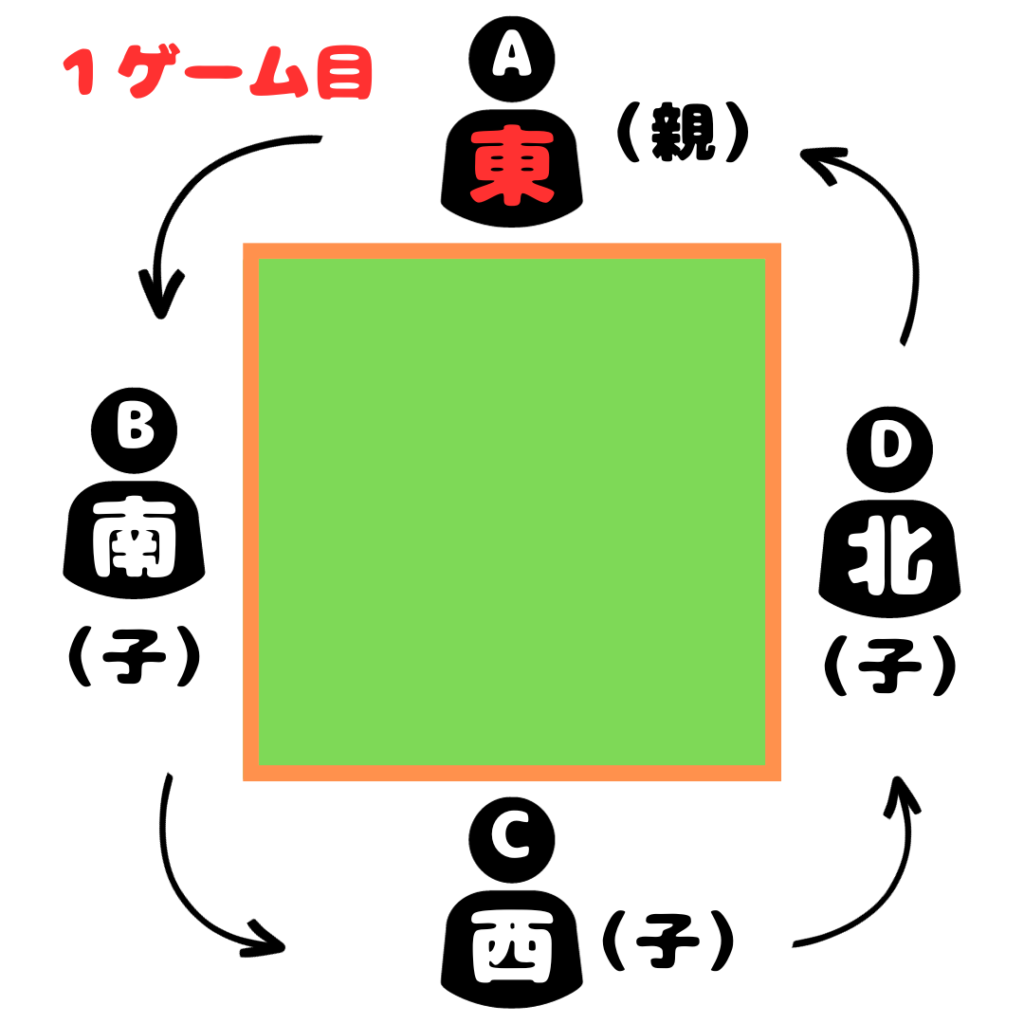
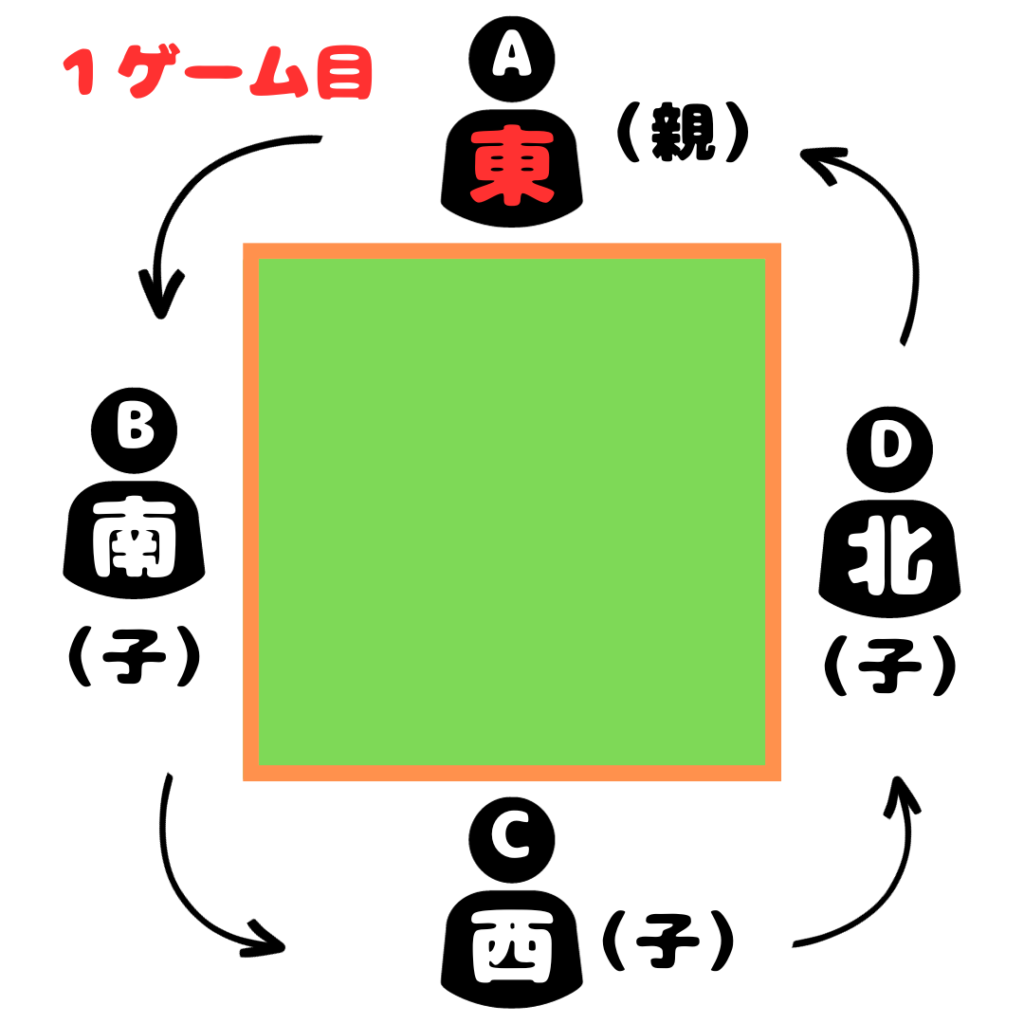


全部で8局または、点数が0点を下回った場合
コールドゲームで試合終了になります。
親が何回も続くケースがあるので、後ほど説明します。
ゲームの流れ
ここまで場について説明しました。
次はゲームの流れついて説明します。
ゲームの流れは
1 場を決める
2 ゲーム開始(25000点スタート)
3 頑張って高い点数を上がる
4 8局戦い、一番多くポイントポイントを持っている人の勝ち
こんな感じです。
具体的に解説していきます。
場の決め方
場の決め方は東南西北方式が一般的です。


まず東南西北を用意し、
裏側にして混ぜます。
その後一人ずつめくって行き、
東を引いた人が
場決めが完了します。
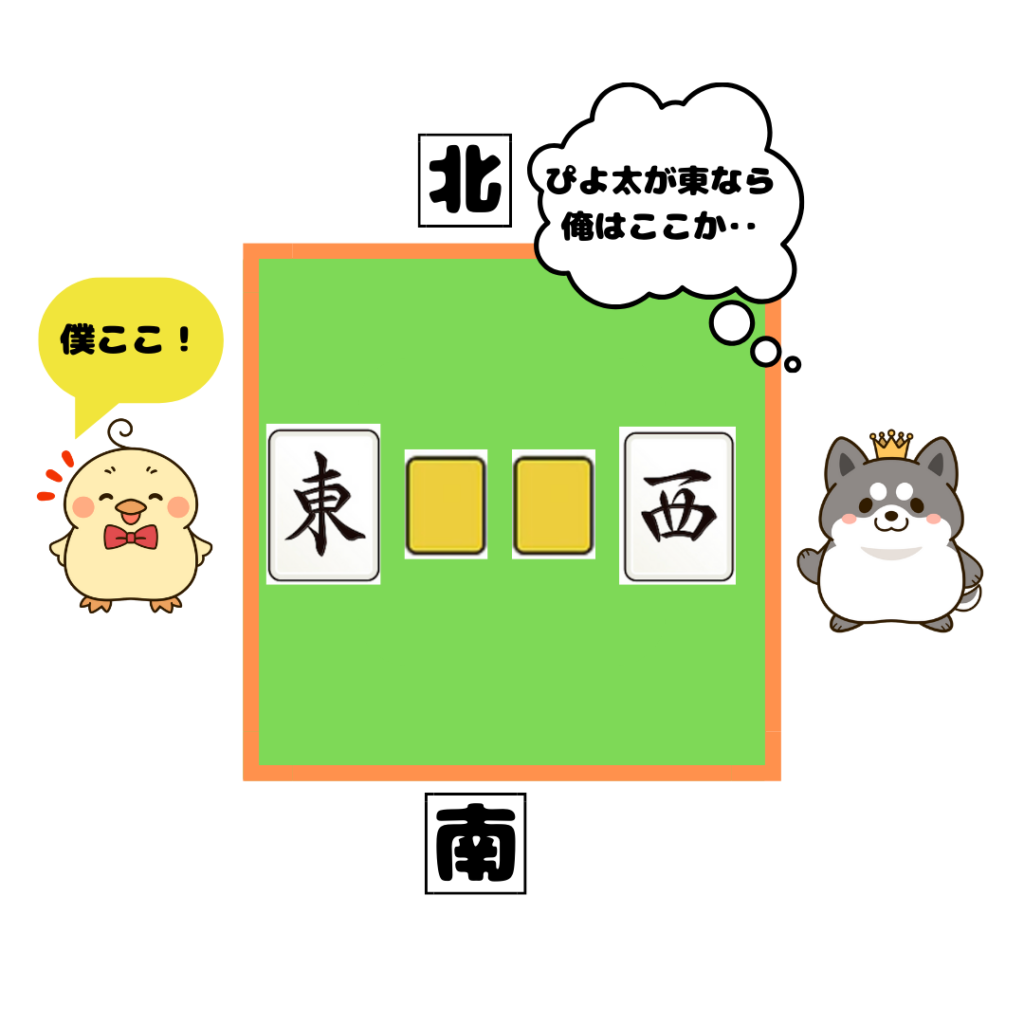
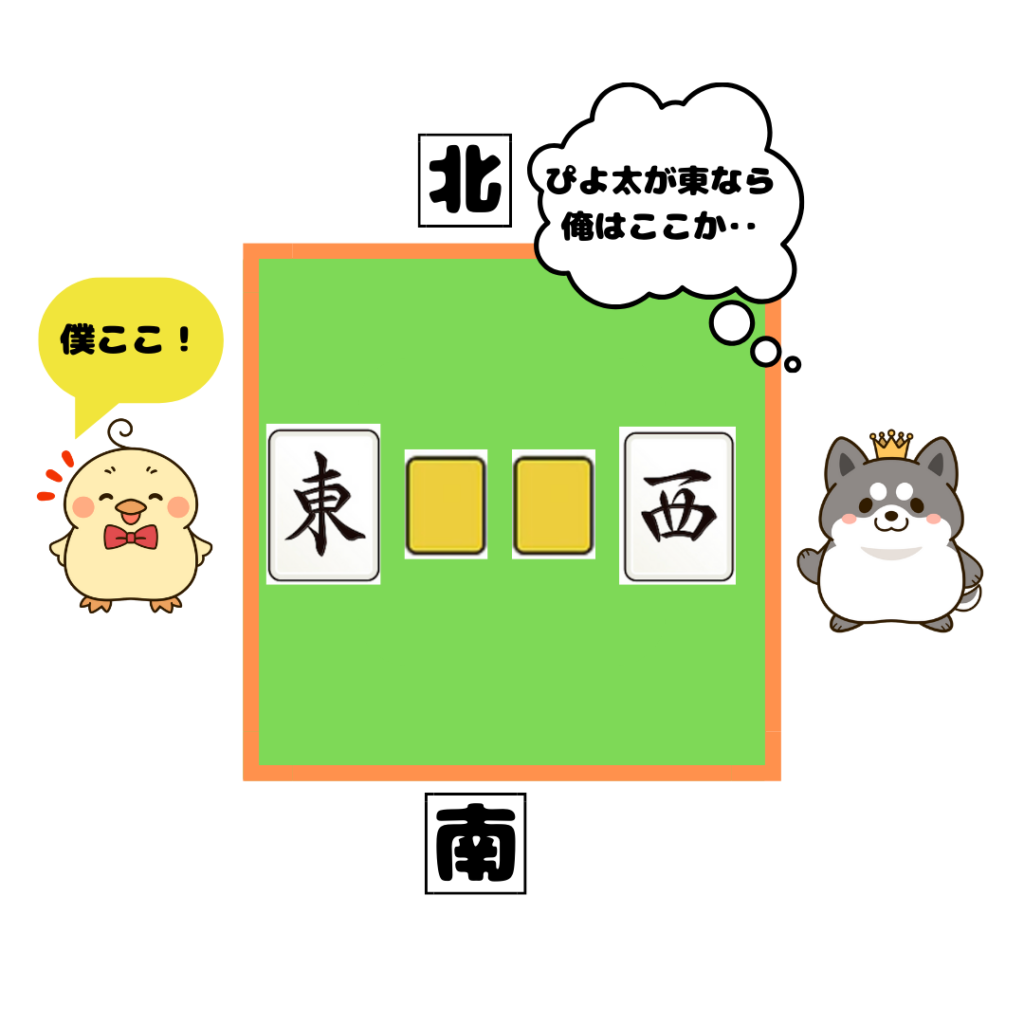
ゲーム開始後
次にゲーム開始後のお話です。
半荘の場合、合計8局やります。
最初は皆25000点スタートです。


その後、人から上がったり(ロン)
自分で持ってきたりして(ツモ)
点数を稼いでいきます。
・ロンの場合
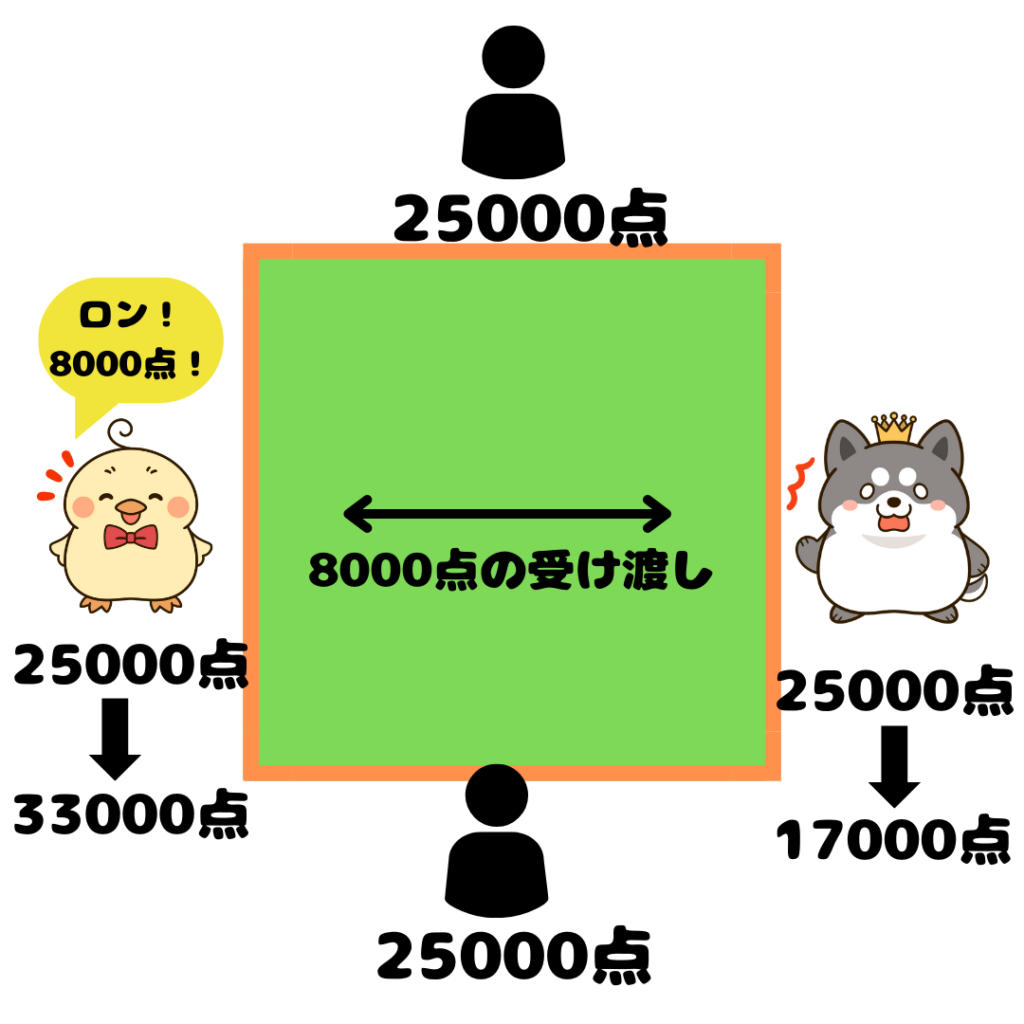
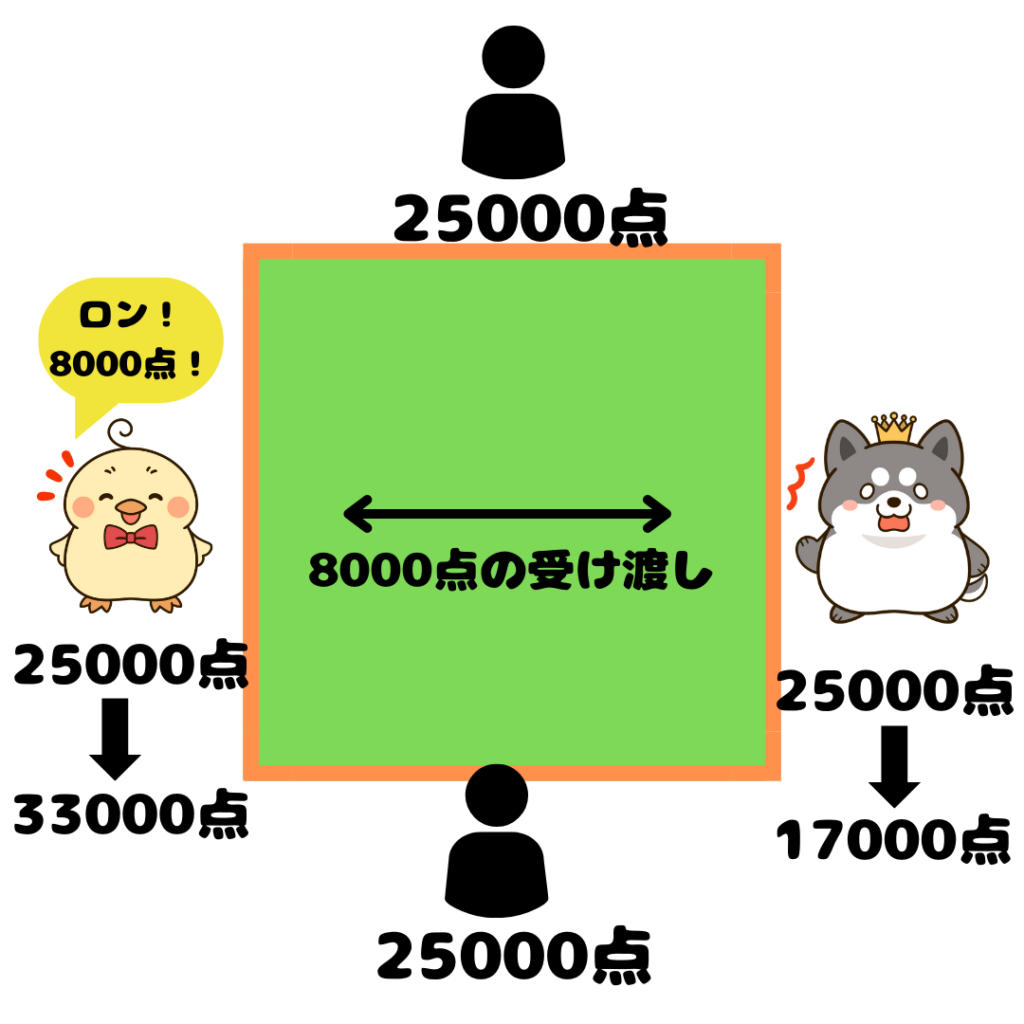
・ツモの場合
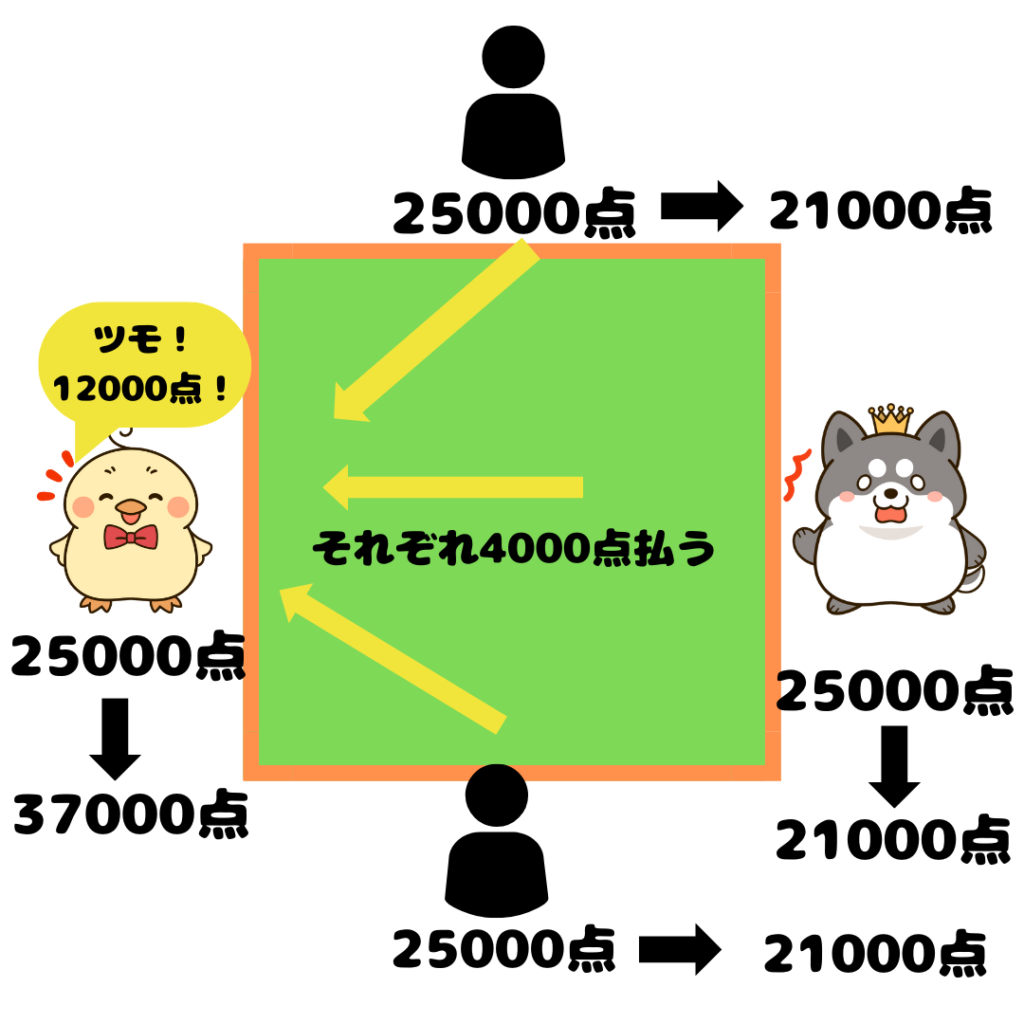
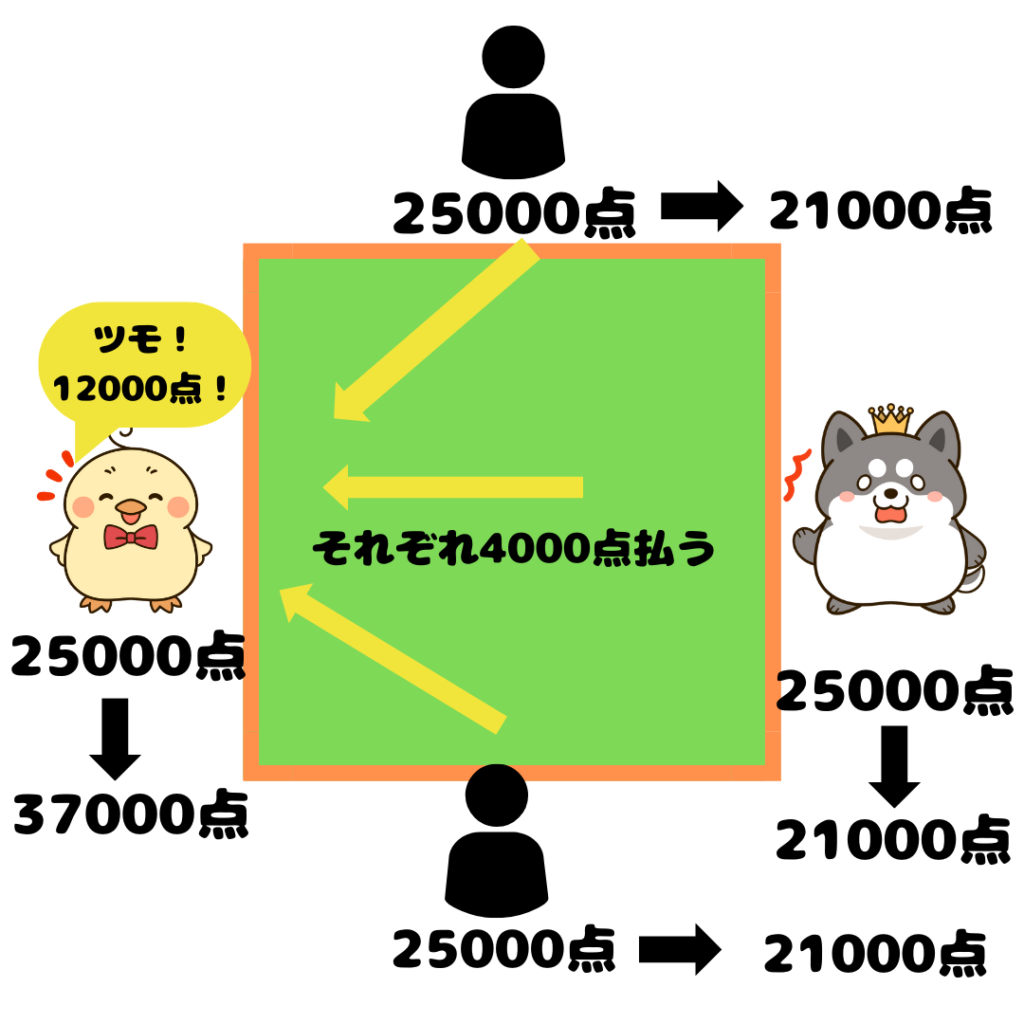
こうやって上がりを積み重ねることで、
点数を増やして行きます。
連荘(れんちゃん)
先ほど親を複数回できるケースがあると
言いました。(ボーナスがいっぱい)
それを連荘(れんちゃん)と呼びます。
連荘できるケースは以下のケースです。
絶対条件→自分が親である時
+
・自分が上がること
・自分がテンパイで流局した時
このいずれかが必要です。
テンパイ=上がれる状態にあること
流局=誰も上がれず、牌がなくなった時
自分が上がるか、上がれる状態で流局した際に
親を続けることができます。
たくさん上がって、たくさん連荘することができれば
自ずと勝利は見えてくるでしょう。
まとめ
いかがだったでしょうか?
今回は場について解説してきました。



頭がパンクしそう‥
新しい単語や概念でパンパンかと思いますが、
まずはさらっとで大丈夫。
アプリでやってみて、流れを掴んでみましょう!
雀魂というアプリが一番ユーザー数が多いので、
おすすめです。
それでは次回もお楽しみに!



本日もサービスサービスぅ!


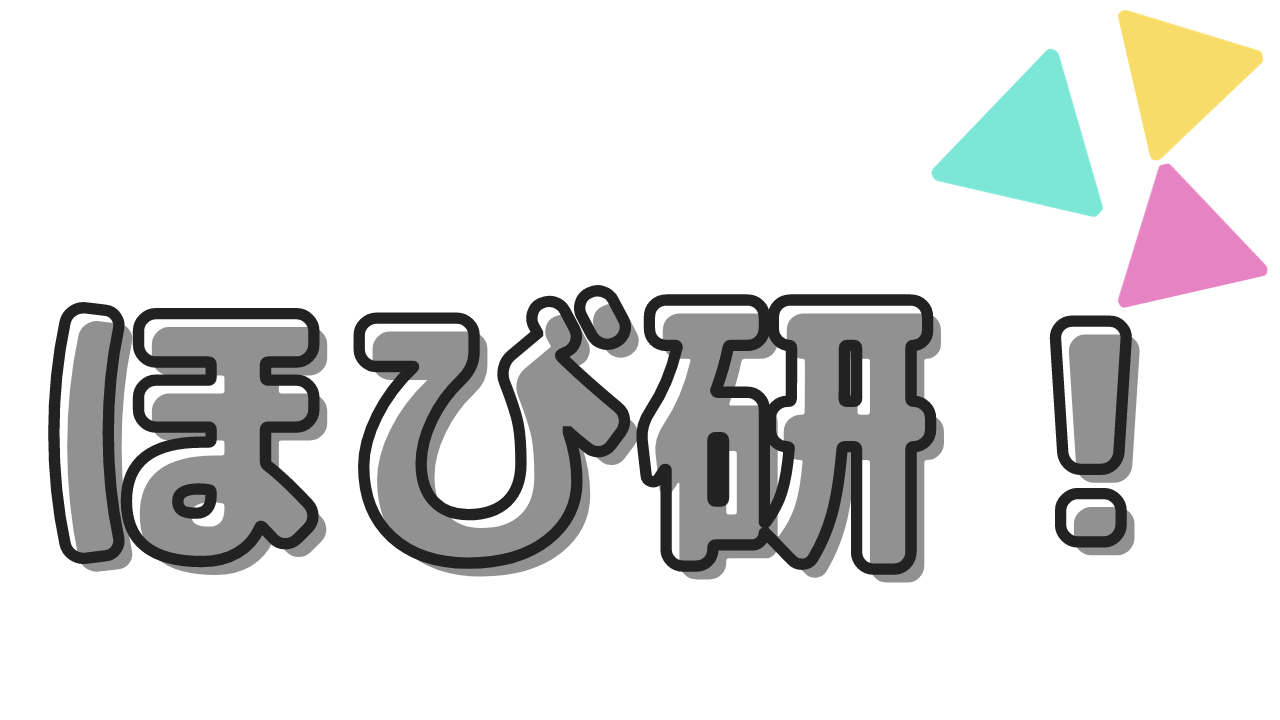
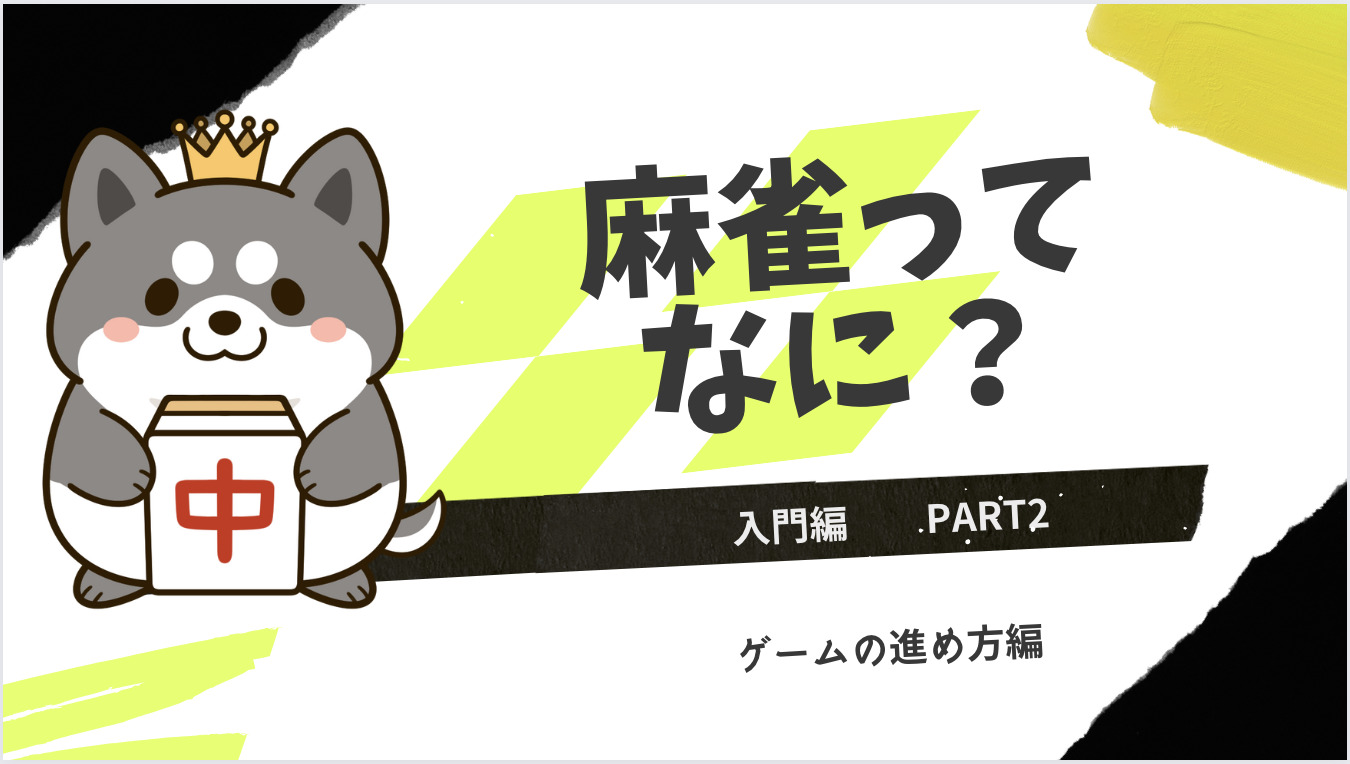
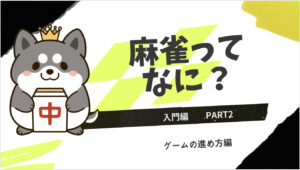
コメント